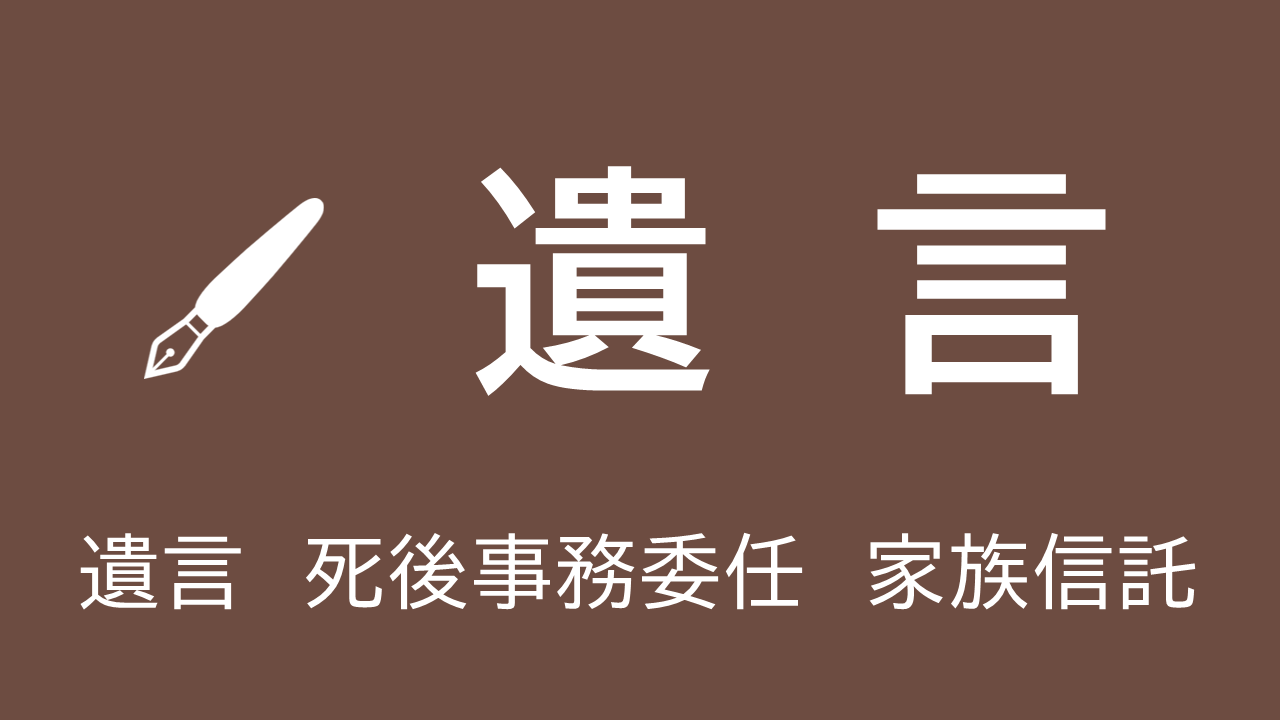家族信託(民事信託)は、2007年に大改正された信託法が施行されたことにより、新たに可能となった手法です。信託とはその名の通り、自分の財産を他人に「信じて託す」ことです。託す人を「委託者」、託される人を「受託者」と言います。従来は、信託銀行等しか受託者となることができませんでしたが、新信託法により委託者の家族等の個人も受託者となることが可能になりました。
家族信託では、従来の遺言等の方法ではできなかった、柔軟な財産の管理、承継が可能となります。
- 自分(委託者)だけでなく、家族のためにも財産を管理、運用させることができる。(信託により利益を受ける人を「受益者」と言います。)
- 次世代以降の(次の次の世代、そのまた次の世代と)財産の承継先を指定することができる。
- 財産の処分方法に制限をかけることができる。(不動産は売却してはいけない等)
- 財産を一度に全てではなく、時期を分けて少しずつ承継させることができる。(例えば、障がいを持つ子や浪費家の子に、毎月必要な額だけ生活費を支給することができます。)
上記はほんの一例で、委託者と受託者の間で合意すれば、基本的にどんな取り決めも自由にできます。また、通常の委任契約は当事者の死亡により終了しますが、信託は委託者の死亡後も終了しません。
1.家族信託の費用
報酬(税込)
信託財産の評価額に比例
- 1億円以下の部分 … 1%(5,000万円以下の場合は、最低額50万円)
- 1億円超3億円以下の部分 … 0.5%
- 3億円超5億円以下の部分 … 0.3%
- 5億円超10億円以下の部分 … 0.2%
- 10億円超の部分 … 0.1%
※信託財産に不動産がある場合、+10万円(2物件以上の場合、1物件ごとに+2万円)
計算例
- 財産額4億円の場合 … 1億円×1%+2億円×0.5%+1億円×0.3%=230万円
実費
公証人手数料
- 「公証人手数料」参照(信託財産の額、契約書の枚数等による)
登録免許税(信託財産に不動産がある場合)
- 固定資産税評価額の0.4%、ただし土地信託の場合は0.3%
その他
- 郵送費・交通費
2.家族信託の注意点
家族信託には考慮すべき点が多数ありますが、特に以下の2点は重要なポイントです。
受託者を誰にするか
家族信託では、信頼できる親族が受託者になることが想定されています。そもそも適任者がいるのかという点が問題になります。
適任者がいたとしても、その人が将来死亡したり何らかの理由で受託者として仕事ができなくなった時に備えて、第2・第3の受託者を考えておく必要があります。受託者=受益者となった場合、1年で信託が終了してしまうので、そのような事態にならないように設計することも重要です。
また、受託者は長い期間に渡って財産を管理する義務を負うため、それに見合う報酬を信託財産から支給したり、信託終了後に残余財産を取得できるようにする等、何らかのインセンティブを与えるような考慮が必要なこともあるでしょう。
なお、司法書士や弁護士等の専門職は受託者になることはできません。信託業法に違反するからです。
予期せぬ課税が発生しないか
通常、当初受益者を委託者とします。最初から受益者を委託者とは別の人にしてしまうと贈与税が発生するからです。(なお、委託者兼当初受益者の死亡をきっかけに二次受益者に受益権が移る際は相続税が発生します。)
民事信託が課税逃れのために利用されないよう、税法には様々な規定があります。民事信託は長期に渡ることも多いので、想定外の事態が起きて予期せぬ課税が発生しないようあらゆるケースを考慮しなければなりません。特に複雑な信託を組成する時は、家族信託に詳しい税理士を交えて充分に検討する必要があります。